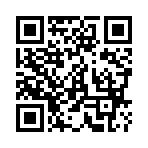2019年03月13日
クジャクのちょんまげ

クリックしてお読みください
ニュース和歌山子ども版 2019年3月13日掲載
わかやま生き物クラブでの観察会
クジャクを観察した、さわさんのはてな

「クジャクのちょんまげはなぜあるの? もしかしたら体温調節するのかな」
さわさんは、以前にテレビで、ゾウは耳で体温調節する ことを見て、クジャクもそうかな と考えたそうです。なるほど。
◆頭の羽(冠羽)
クジャクのちょんまげは、頭の羽が長くのびたもの。冠羽(かんう)といいます。
クジャクの冠羽は、オスにもメスにあり、オスの冠羽はあざやかな青色です。
冠羽にはどんなはたらきがあるのだろう?
たとえば、カンムリヅルの華やかな冠羽。
緊張したり、気持ちが高まったりした時に、ぶわっと広がった場面を見たことがあります。

天王寺動物園のカンムリヅル
クジャクも、ちょんまげ(冠羽)を、広げるでしょうか

改めて観察してみると、、
冠羽の広がりは確認しなかったのですが、
じっと観ていて、ポケットさんがへーっと気づいたことは

クジャクがよく頭を小刻みに動かすこと
そのたびに、頭の青い羽が陽射しに反射してきらきら輝くこと
 でした。
でした。飼育員さんによると、クジャクの冠羽は1本ずつ生えかわり、繁殖期が終わる秋に、わりと多く、抜けるようです。
クジャクのオスが羽を広げて、メスに求愛するのも春から夏。
ちょんまげのあざやかな色も、もしかしたら、自分をPRする効果を高めることに関係するかもしれません
あくまでもポケットさんの勝手なすいりなので、皆さんで実際に観察してしらべてくださいね。
◆いつからちょんまげ?
発達の要因で、クジャクの冠羽を考えてみましょう。
飼育員さんの記録では、孵化(ふか)したてのヒナには冠羽はなく、孵化後、約1ヶ月で生え揃うそうです。
可愛いですね


写真 和歌山城公園動物園 飼育員 結城優里さん提供
インドクジャク 孵化後約1ヶ月のヒナと母親
◆とさか
体温調節に関わるちょんまげを、動物園内で見つけました!
ニワトリのとさかです。とさかは皮膚が発達したもの。細かな血管が通っています。
白クジャクとニワトリのちょんまげツーショット

さわちゃんが寄せてくれた「はてな」のおかげで、ポケットさんも、鳥の頭が気になるようになりました。
◆ちょんまげいろいろ
アオサギ(天王寺動物園で撮影 2019年2月16日)
モモイロペリカン(和歌山城公園動物園 2018年12月14日)
ほかにもいろいろなちょんまげがあります。
どんなはたらき?、いつ生えるの? など、調べたら教えてね。
2019年02月27日
鳥の体重どれくらい?

クリックしてお読みください
ニュース和歌山子ども版 2019年2月27日掲載
前回に続いて、和歌山大学教育学附属小学校第4学年の子どもたちからの疑問
「フラミンゴの脚(あし)はあんなに細長いのに、どうして体を支えられるの? もしかしたら体重が軽いから?」
なるほど、体重と関わらせて考えたんですね

そこで、
ポケット「フラミンゴの体重、どれくらいかな?」
子どもたち「15キロくらい」 「20キロくらい」
「だって人間だったら、足とかに筋肉あるから、その分重いやん。でもフラミンゴやったら足が細いし、そんなに筋肉がなさそうやし」
少なく見積もって、15~20キロくらいと予想しました。
でも調べてみると、フラミンゴは大体2~4㎏(しかありません)。 子どもたちはえー!と驚きました。

◆体重と軽い骨
空を飛ぶ鳥は、骨がうすく軽いしくみになっています。
ポケットさんの自宅にある、フラミンゴの頭の骨。 わずか10グラム。1円玉10枚分の重さしかありません。

手の平にのせても、ふわっとした感触。
ちなみに、空を飛ばない鳥の体重を調べて見ると、
ペンギンは体が小さいですが、フラミンゴとほぼ同じ体重。
エミューは約50キログラムで、人間のおとなくらいの体重があります。
◆バランスのよい骨の配置
フラミンゴが、あの細長い脚(あし)で安定して立てるのは、骨の配置のバランスと関係があります。
『鳥の骨探 エヌ・ティー・エス』 のデータ
フラミンゴの骨の長さ
脚の甲(足根中足骨) 34cm
脚のすね(脛足根骨) 36cm
甲とすねの長さがほぼ同じ。
バランス良く立てる配置になっています。
それも1本足でずっと。。
フラミンゴのまねをして1本足で立ってみよう。どれくらいの時間、たっていられるかな?
2019年02月13日
フラミンゴの脚の筋肉

クリックしてお読みください
ニュース和歌山子ども版 2019年2月13日掲載
小学校理科第4学年では、「人の体のつくりと運動 骨と筋肉」を学びます。
動物の骨と筋肉を、本物を観察して学ぼうと、和歌山大学教育学部附属小学校第4学年の子どもたちが、学校のすぐ近くにある、和歌山城公園動物園で授業を行いました。
動物園での観察♪
「あしをどうつかうかな?」
先生が動物園に持参した骨模型

ヒトの骨とくらべてみる
ポケットさんも、授業に呼んでいただき、動物の骨と筋肉のはてな
 を、一緒に考え、話し合いました
を、一緒に考え、話し合いました

子どもたちとの対話内容を、先生が板書してくださったもの(一部)です。
今回は、はてな?が多く出た、フラミンゴのながーい脚(あし)
 についての疑問
についての疑問「フラミンゴの脚に筋肉がない・・?」
確かに細長い脚(あし)は、綿菓子の棒のようで、筋肉がないように見えます。
まず、あのながーい脚は、私たちの脚の、どの部分かを確認してみると、
フラミンゴの脚の真ん中あたりのふくらんだ部分は、私たちの足首、かかとになります。 ひざではありません。
だから曲がり方はこうなります
 違和感がありますが、、
違和感がありますが、、神戸市王子動物園で撮影した休息するフラミンゴ。
私たちが立っている姿勢と同じ状態です。
つまり、フラミンゴの長い棒のような脚は、私たちの足の甲と、すねの骨がそれぞれ長くなっている部分です。
筋肉は膝(ひざ)から上に多くついていて、外からは見えにくくなっています。
空を飛ぶ鳥類は、体の重心に重い筋肉を集めたつくりになっています。
すると、子どもたちから 「フラミンゴって空を飛ぶの??」
動物園では、空を飛ぶイメージがわかないのかも。。

フラミンゴは、餌となるプランクトンが発生する水場を求めて、たくさんの群れで空を飛び、移動します。
野生のくらしも調べてみてね。
関連記事 朝日新聞和歌山版「わかやま動物ウオッチング」
参考になる本 『骨と筋肉大図鑑3 鳥類 学研教育出版』

2018年11月28日
鳥の耳と聞こえ方

クリックしてお読みください
ニュース和歌山子ども版 2018年11月28日掲載
小学校3年生のこうきさん(和歌山市内)から、飼っているセキセイインコの「はてな?」が届きました

「耳の形で聞こえる範囲はどう違いますか?インコを飼っていて、遠くの仲間の声に反応します。ウサギのような大きな耳がついていないのに・・・。ウサギの耳は意味があるのでしょうか?」
なるほど、耳の形と音の聞こえ方との関わりを考えたんですね!

こうきさんが飼っているセキセイインコ
 1才のメス
1才のメス羽毛にかくれて、耳がどこにあるか、見えませんね。それでも、音は良く聞こえている♪
今回は、耳の構造と音が聞こえるしくみ、そして、鳥の音の聞こえ方 を調べてみましょう。
◆耳のしくみ 音はどのように聞こえる?
参考にした本 くらべてみよう!人と動物のからだ4/ポプラ社

音を聞くこととは、ものがおこした振動(しんどう)を感じ取ることです。
耳介(外から見える、頭からでっぱった耳)であつめられた振動(しんどう)が、耳のあなを通って、鼓膜(こまく)に伝わります。
鼓膜(こまく)のしんどうは、小さな骨をつたわり、脳に送られ、音として聞きます♪
 インコなどの鳥には、でっぱった耳介(じかい)がみあたらないけれど、耳の穴がちゃんとあります。
インコなどの鳥には、でっぱった耳介(じかい)がみあたらないけれど、耳の穴がちゃんとあります。エミューの耳の穴!! 羽毛がまばらなのでよくわかります。
音はどの程度聞こえているのでしょうか?
◆鳥の音の聞こえ方
こうきさんのインコは音をどう聞いているのかな?
ポケット「遠くの仲間の声に反応するとは、どこにいる、だれのことかな? どのように反応するの?」
こうき「家の外にいるスズメや、ピッピと鳴く鳥の声が聞こえると、ピュイピュイと大きな声で鳴きます。その鳥の姿は見えない。でも、カラスの声には返事をしない。こわがってカゴの奥に逃げる」
飼っているインコは、スズメとカラスの音を聞き分けていることを、こうきさんは気づいているんですね!

ほかにも、パチッパチッと爪を切る音や、ハンガーを物干し竿にカチャカチャとかける音にも反応するそうです。
動物によって、音の聞こえる範囲(周波数:振動する数)は異なります。
たとえばつぎの種類の、聞こえる最大の音の高さ(最大周波数)は、
「数値でみる生物学/シュプリンガージャパン」に、こう書かれてありました。
本によってデータは違うので、参考として見てください。
カラス 8kHz(キロヘルツ)以下
カワラバト 12kHz
☆セキセイインコ 14kHz
スズメ 18kHz
コマドリ 21kHz
ちなみに ヒト 21kHz

鳥は、複雑な音を聞き分けられるようです。(鳥の生活/平凡社)
音の1つ1つのパルス(信号、脈のように動く回数)を
人間は1秒に20個聞くのに対して、
鳥は1秒に200個も聞けるそうです!!

地鳴き、警戒音、さえずりなど、鳥は様々な音色を出し、聞き分けています。
野生のセキセイインコは大きな群れでくらします、鳴き声でいろいろなコミュニケーションをとるのでしょうね。
こうきさんのセキセイインコは、豊かな音の世界を感じているんですね♪♪
でも、もし鳥に耳介があったら、もっとたくさんの音がきけるのでは?
◆鳥に耳介がないのは?
先ほどのエミューの写真では、少し、耳のふち(耳介)があるように見えます。
でも鳥には、音を集める耳介がほとんどありませんね。それはなぜだろう?

『鳥たちの驚異的な感覚世界 河出書房新社』 には、このような説が紹介されていました。
・羽が耳をおおい、飛ぶ時に空気をスムーズに流したり、水に潜る時に水が耳の中に入るのを防ぐ
・飛行への適応ともいわれるが、鳥の祖先の爬虫類は耳介をもっていないので、飛ぶことと関わって耳介を失ったかどうかは不明
なので、祖先も耳介がないから、鳥にもない とも考えられる
つまり、4つのアプローチでの、進化 での説明になります。
とすると、私たちを含めた、哺乳類に、なんでこんな耳(耳介)があるのかが、不思議になってきますね。
耳介 の はたらき は 次回 に! しゃれになってしまいました