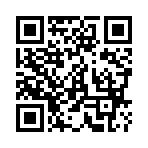2018年12月12日
耳の形とはたらき

クリックしてお読みください
ニュース和歌山子ども版 2018年12月12日掲載
前回のつづき。こうきさんからの、「ウサギの大きな耳はなぜ?」 について考えてみましょう。
鳥には顔から張り出した大きな耳(耳介)がありませんが、哺乳類(ほにゅうるい)はいろいろな形、大きさの耳をつけています。
それはなぜだろう?
前回紹介した本、『鳥たちの驚異的な感覚世界』では、
「哺乳類で耳介が発達したのは、夜に活動するグループが聴覚(ちょうかく)を働かせていたことと関係するのでは?」 と書いてあります。
空を飛ぶ夜行性のコウモリは大きな耳をもっていますね。
哺乳類の耳には、どんな はたらき があるかな

◆耳はアンテナ
手を耳にあててみてください。よく聞こえますね

耳介には、音を集めるはたらきがあります。 耳を動かせば、あちこちの音がひろえまね。
多くの哺乳類は、耳介を動かす筋肉が発達しています。(私たち人間は、耳をほとんど動かせませんが、、)
ウサギもこのように 耳を左右別々に動かして、周囲の音をキャッチします。
片方の耳だけ立たせたカイウサギ
◆気分の表現
ウマや我が家のネコなどは、警戒したり、おこったりするときに、耳をふせます。
今、どんな気分

耳はきもちを表わすサインにもなります。
あなたが飼っている動物の耳はどう動きますか? そのとき、その動物はどんなきもちだろう?
◆熱をにがす
ウサギやゾウは耳の血管から熱を逃がして体温を調節します。
京都市動物園のアジアゾウ
耳の裏側の血管に注目

暑い時は、耳をぱたぱた動かして、血管に風をあてて、熱を逃がします。
ゾウの自前の耳うちわです

そして、哺乳類(ほにゅうるい)の中でも、耳がそれほど大きくない(頭からはりだしていない)動物もいます。
たとえば、ミーアキャット
アメリカビーバー
どんな環境でくらすのかな?
耳の形と関係はあるかな?