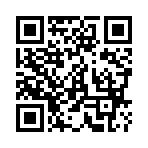2024年07月20日
ツキノワグマ ベニーちゃん、どうもありがとう
7月18日に、和歌山城公園動物園で長年、市民に愛され続けていた、ツキノワグマの「ベニー」が亡くなりました。
和歌山市の広報をご覧ください。
https://www.city.wakayama.wakayama.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/059/325/20240719.pdf
野生の大使として、つまり日本の森林の生態系の一員である、ツキノワグマを代表として、ベニーちゃんは、動物園でいろいろなことを伝えてくれました。
私たちの心のよりどころにもなってくれました。
ベニーちゃんとの思い出、ツキノワグマとしての大切な記録を、できるだけ残したいと思います。
皆さんの思い出や、残してほしいことを、是非、お伝えください。
動物園は、博物館の一種です。
動物園にいてくれている、動物たちの記録をしっかり残し、野生生物や私たちが互いに生きていくことにつなげていく役割があります。
皆さんの声をおまちしています!
ベニーちゃんのご冥福を心からお祈りいたします。 本当にどうもありがとう。
和歌山市の広報をご覧ください。
https://www.city.wakayama.wakayama.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/059/325/20240719.pdf
野生の大使として、つまり日本の森林の生態系の一員である、ツキノワグマを代表として、ベニーちゃんは、動物園でいろいろなことを伝えてくれました。
私たちの心のよりどころにもなってくれました。
ベニーちゃんとの思い出、ツキノワグマとしての大切な記録を、できるだけ残したいと思います。
皆さんの思い出や、残してほしいことを、是非、お伝えください。
動物園は、博物館の一種です。
動物園にいてくれている、動物たちの記録をしっかり残し、野生生物や私たちが互いに生きていくことにつなげていく役割があります。
皆さんの声をおまちしています!
ベニーちゃんのご冥福を心からお祈りいたします。 本当にどうもありがとう。
2023年11月09日
ゆたかさってどんなこと?大牟田市動物園イベントのお知らせ
皆さん、こんにちは。
今回は、私(ポケットさん)が一緒に参加する、大牟田市動物園のイベント(連続オンライン教室)をご案内します。
案内および申し込みは下記です!
https://omutacityzoo.org/announce/?p=4875
テーマは 「ゆたかさってどんなこと?」
大牟田市動物園は、「動物福祉」をテーマにしている動物園です。
この教室では、「動物にとってのゆたかさ」や「自分(たち)のゆたかさ」を自由に話し合います。
そして、大牟田市動物園の動物たちが、よりゆたかにくらせるアイデアを考え、飼育員さんと一緒に試してみます。
これはなかなかできない機会です!
対象は小学校4~6年生の皆さん
11月から3月まで、毎月1回、13時から14時の1時間のプログラムです。
参加無料
1. 第 1回 2023年 11月26日「ゆたかさってなんだろう?」
2. 第 2回 2023年12月17日「動物園での取り組みを見てみよう」
※できましたら冬休みの間に、お近くの動物園にお出かけください。
3. 第 3回 2024年 1月28日「どんな工夫ができるか考えよう」
4. 第 4回 2024年2月11日「どんなことができるか選ぼう」
5. 最終回 2024年 3月10日「結果を見てみよう」
締め切りは11月20日です。
全国どなたでも、海外からの参加も可能です。
動物福祉、動物のしあわせ などに興味のあるお友達にもお伝えください。
今回は、私(ポケットさん)が一緒に参加する、大牟田市動物園のイベント(連続オンライン教室)をご案内します。
案内および申し込みは下記です!
https://omutacityzoo.org/announce/?p=4875
テーマは 「ゆたかさってどんなこと?」
大牟田市動物園は、「動物福祉」をテーマにしている動物園です。
この教室では、「動物にとってのゆたかさ」や「自分(たち)のゆたかさ」を自由に話し合います。
そして、大牟田市動物園の動物たちが、よりゆたかにくらせるアイデアを考え、飼育員さんと一緒に試してみます。
これはなかなかできない機会です!
対象は小学校4~6年生の皆さん
11月から3月まで、毎月1回、13時から14時の1時間のプログラムです。
参加無料
1. 第 1回 2023年 11月26日「ゆたかさってなんだろう?」
2. 第 2回 2023年12月17日「動物園での取り組みを見てみよう」
※できましたら冬休みの間に、お近くの動物園にお出かけください。
3. 第 3回 2024年 1月28日「どんな工夫ができるか考えよう」
4. 第 4回 2024年2月11日「どんなことができるか選ぼう」
5. 最終回 2024年 3月10日「結果を見てみよう」
締め切りは11月20日です。
全国どなたでも、海外からの参加も可能です。
動物福祉、動物のしあわせ などに興味のあるお友達にもお伝えください。
2019年11月13日
ビーバーのしっぽの使い方
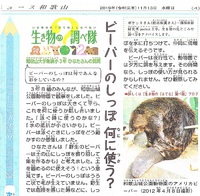
記事をクリックしてお読みください
ニュース和歌山子ども版2019年11月13日掲載
和歌山大学教育学部附属小学校3年B組さんの道徳教育と総合的な学習の時間で、2回、動物の出張授業をさせていただきました
1回目は教室で。動物と自分たちがどう関わっているかな? 生命のつながりについて、意見を交わしました。
そして2回目は動物園で。動物のきもちになって、よーく観察しようをテーマに、興味のある動物を観察しました。
もともと、ビーバーのしっぽに興味があったひなたさんは、友だちと、変わった形のしっぽを何に使うか話し合いました。
平たくて毛がなく、ぶつぶつとうろこ状になっているしっぽの使い道。
ちなみにポケットさん宅に、ビーバーのしっぽの標本があるので、写真を紹介します。


ひなたさんが考えたように、うちつけるのに便利そうですね。
このとき、ビーバーは小屋の中で寝ていて、動きの観察ができませんでした。
でも、寝る・休む ことも 行動の一つ
以前に撮影した 泳いでいる様子
夕方の餌やり後 食べている様子
実際の動きは、自分でしっかり観察して確かめてね

2019年11月03日
イモリのおなかの模様

画像をクリックしてお読みください
ニュース和歌山子ども版 2019年10月9日掲載
今回は、疑問に思ったことを自分たちで調べた自由研究の紹介です!
あいささんと、みどりさんの姉妹は、あらぎ島(有田川町)の田んぼにいたアカハライモリ2匹を地元の人にもらって、去年の6月から自宅で飼っています。
1匹は赤いおなかに黒のぎざぎざ模様で、もう1匹は点点模様。2匹で模様が違うことに興味をもちました。
そこで、アカハライモリを飼っているところへ調査しにいきました。
1匹ずつおなかの写真をとり、体の大きさを測りました。
和歌山市立こども科学館、和歌山県立自然博物館、田辺市ふるさと自然公園センター
自宅にいる2匹、計29匹のデータを集めました

そして、先行研究を参考にして、AからFまでのカテゴリーをつけて、模様の分類をしました!
A:模様が少ない
B:黒い点が多い
C:黒い列
D:いろいろな模様
E:黒い線が波のよう
F:とても複雑
参考にした論文 中津(2019)「大阪府におけるアカハライモリの分布と腹面模様の変異」,爬虫両棲類学会報2019(1)
すると、調査したイモリはCDEタイプが多く、田辺の7匹は似ていたそうです。
みどりさんは、29匹の模様の絵をすべて描いて、学校に提出したそうです。すごい記録ですね!!
姉妹は、行動もよく観察しています。
1匹はとても活発で、もう1匹は行動がゆっくり。
けんかはせずに、すきまに入るのが好きだそうです。
ストレスをあたえないようにと、きづかっていました

2019年10月08日
ノウサギとカイウサギの違い

画像をクリックしてお読みください
ニュース和歌山子ども版 2019年9月11日掲載
和歌山市立有功東小学校6年光組さんの総合学習で、ポケットさんが7月4日に出張授業に伺いました。
参考:和歌山県環境学習アドバイザー派遣事業
テーマは、「野生動物とペットとの違い」 そして 「動物を飼うこと」について

子どもたちの問題意識
まず、学校の校庭に、ノウサギの糞がたくさんしてあること。
なぜこんなに? 地域の人が校庭を使う時に困る 畑で栽培したイモの新芽を食べられる
そして、6年光組さんは、学校敷地内にあるネイチャールームを整備していること。
ここに飼育小屋があるので、何かを飼いたいという希望が出ている
そこで、ノウサギを捕まえて飼育小屋で飼ったら?という案が出たとのことです。
そこで子どもたちと、野生動物と家畜(ペットを含む)との違いについて考えを出し合いました。
たとえばこんな意見がありました。
「野生動物には菌があるから、さわったりかまれたりするとよくない」
「ペットのウサギは丸っこい」 など。
皆さんは、どんな違いがあると思いますか?
同じウサギでも、野生動物のノウサギと、ペットなどで飼われるカイウサギは、習性も、生まれてくる様子も、人とのかかわりについても異なります。
まず、「ノウサギ」は、日本にしかすんでいない(日本固有種)、野生のウサギの種類名です。
つまり野生のウサギ全てをノウサギというのではなく、「ノウサギ」 という名前のウサギ (ライオン トラ と同じような種類名)です。
日本にすむ「ノウサギ」のうち、日本海側など積雪地帯にいるノウサギは、冬に毛色が白く変化します。
和歌山県内でみられる、太平洋側にくらすノウサギは、年中茶色です。
一方、「カイウサギ」、アナウサギ というウサギの種類から、改良されたウサギで、巣穴を堀り、未熟な赤ちゃんを産みます。
ノウサギはしっかりした巣穴をつくらず、生まれたばかりのノウサギの赤ちゃんは、お母さんのミニチュアのように発達してしっかりしています。
ノウサギは、とても神経質で飼育は困難です。
ポケットさんが前に仕事をしていた多摩動物公園でも、かなり難しい技術を必要としました。
野生動物は人間と距離をおきくらしています。
また、鳥獣保護法でも、許可なく、野生の哺乳類や鳥類を捕獲、飼養することは禁止されています。
そして、カイウサギを飼う場合でも、アナウサギの習性をよく勉強して、生涯責任をもって、心も体も健康に幸せにくらせるよう、命を大切にして飼うことが大切です。
ネイチャールームには、小さな水場や昆虫が寄ってくるようなビオトープもあります。
豊かな自然に囲まれた小学校に、地域の人や学校の子どもたちが集い、様々な生物と交流できる場所になったら素敵でしょうね


2019年09月12日
セミの抜け殻調べ

画像をクリックしてお読みください。
ニュース和歌山子ども版 2019年8月31日発行
8月18日に、和歌山県生物同好会との共同開催で、わかやま生き物クラブの観察会「セミの抜け殻調べ」を行いました。
講師は、元和歌山市子ども科学館の土井浩先生。
森がある和歌山城公園(動物園付近)と、道路に面した汀公園とで、ぬけがらを採りました。
木々に囲まれた和歌山城公園 ミンミンゼミの声も聞かれました
汀公園 道路に面しています
勤労者総合センターで、集めた抜け殻を調べました。うわ、こんなにたくさん!!

種類をみわけるポイントは 大きさ 形 触覚の節の長さ
でべそがあれば クマゼミ☆
それぞれカウントして、数を足して、割合を出して。 計算がとくいな小学生が、暗算で教えてくれました!!
セミ以外にも、いろいろな生き物を見つけました


おわりに、環境との関わりや、自分のくらしとのつながり などを、考えました。
参加者からは、たとえばつぎのような感想が寄せられました
「セミが環境のものさしになるのが面白かった。ほかにどんな生き物が指標となるのか知りたい」
「自分の家のまわりでも調べてみたい」
「ぬけがらの形がなぜ、こう違うの?」
和歌山経済新聞が記事で紹介してくださいました♪ 以下のサイトをお読みください

https://wakayama.keizai.biz/headline/1423/
2019年08月14日
ネコとイヌの身体能力

画像をクリックしてお読みください。
ニュース和歌山子ども版 2019年7月10日発行
ポケットさんは犬(ボーダーコリー「ブライトくん」1998年8月15日生まれ)と猫(キジネコ「ミュートくん」1998年2月19日) の両方を飼っていました。
感じた違いは、猫は体がしなやかでくねくねしていて、犬は背中が固くがっちりした体つき。
猫は歩み寄ってきてもほとんど足音がしないけれど (来るまで気がつかないことも)
犬はカチャカチャ どすどす と、賑やかです。
猫は高い所が得意でカーテンレールの上を歩いたこともありました。
一方、犬はひたすら走るのが好きで階段を下りるのは苦手でした。(降りるのが嫌と、フンフンと鼻を鳴らしていました)
この違いは、ネコ類は森林、イヌ類は草原に適した体つきや狩りの仕方と関係があります。
ブライトくんとミュートくんは、兄弟のように仲良しで、いつも一緒にいました。
そんな時でも、ブライトくんは床の上。ミュートくんはテーブルや椅子の上など、高い所が好きでした


なお、家の高い塀を行き来できる野良猫が、地域住民の生活環境に被害を与えている問題があります。
和歌山県動物愛護条例では、「飼い猫以外の猫への給餌等の一般的ルール」を定めています。人と猫が良い関係で共に暮らせるよう考えていきましょう。
2019年07月08日
カニに似たヤドカリ

クリックしてお読みください
ニュース和歌山子ども版 6月26日掲載
6月16日、加太海岸で、和歌山県生物同好会主催の磯の生物観察会が開催されました。
潮が引きつつある磯には、多種多様な生物がたくさんいました。
様々な貝類!! 模様や色が少しずつ違う 命名もユニーク ウノアシガイ ヨメガカサガイ ヒザラガイなど
魚、ヒトデ、ウニ、ナマコ、カニ、ヤドカリ、、
アゴハゼの向こうにいる赤い触角の主は? → ケアシホンヤドカリ です!!
こちらは、種類が異なるホンヤドカリ。触覚は赤くありません。
そしてこちらも ヤドカリ!? カニにそっくりだけれど、歩く足が左右3本ずつで、触覚は長いです。 その名も「イソカニダマシ」
はてな?を教えてくれた、りほさんとこうきさんは、カニそっくりのイソカニダマシに驚いたそうです。
「ヤドカリの仲間なのにどうしてカニに似た姿なんだろう?」
「変身した?」「いっぱい食べてカニみたいになった??」
このとき、採取した、貝をつけていない、ケアシホンヤドカリ を見ました。
貝がないと、たよりなさそう、、

そこで考えたのが、「すみかになる貝がみあたらなくて、カニのような形に進化したのでは?」
様々な姿かたちのヤドカリが、食べ物やすみか、いろいろな生き物や環境とどうかかわってくらし、長い年月を経て進化してきたのか
思いをめぐらせたひととときでした

この夏、ぜひ、磯で遊んで、いろいろな生き物を見つてね

2019年06月18日
ネコザメのトゲ

クリックしてお読みください
ニュース和歌山子ども版 6月12日掲載
すさみ町立エビとカニの巡回水族館が、根来山げんきの森の里山まつり(4月29日)にやってきました!!
タッチプールでは、ウニ、ナマコ、ヒトデ
ウニを手の平において少しゆらすと、細長い管足がでてきた。手にひっつくよ
別のプールには何とサメも!! 「噛まない?」 と子どもたちはおそるおそる

ネコザメ、テンジクザメ、イヌザメ いずれもおとなしいサメで、じっとしていました。
触った感触は、ネコザメが一番ざらざらしていて、イヌザメは比較的なめらか。
そして、ネコザメだけが、2つの背びれそれぞれに尖ったトゲをつけていました。
ネコザメは海底の海藻が生える場所などで昼間はじっと過ごし、テンジクザメやイヌザメは珊瑚礁などでくらします。
皮膚の構造やとげの有無は、すみかや天敵などと関連するかもしれません。
同じサメでも、多種多様。 水族館でくらべて観てね。
2019年06月10日
幼虫の見分け方

クリックしてお読みください
ニュース和歌山子ども版 2019年5月22日掲載
4月14日、根来山げんきの森倶楽部の子ども昆虫調査隊に参加しました!
昆虫調査隊は、2007年に発足して以来、毎月定期的にげんきの森内の昆虫の生息状況を調査しています。
講師は 奈良県川上村森と水の源流館 古山暁さん(こやまっち)
4月半ばの調査で、小さな昆虫の子どもを発見!
長い触角! 背中の筋は1本。 草やぶや木の上など、高いところにいる ヤブキリの幼虫
 だとわかりました。
だとわかりました。そういえば、この森では、夏の観察会で、大きく太ったヤブキリ成虫の姿をよく見かけます。
4月ではまだこんなに小さな体なんですね。生命のめぐりを感じました

これから脱皮をくりかえしおとなになっていきます。おとなになって翅が伸びると、こすり合わせて鳴くようになります。
昆虫調査隊は、毎月おこなっています。
講師の古山暁(こやまっち)さんからの6月調査隊のレポートをご報告します!!
調査日 6月9日(日)10時~
見つけた昆虫
ヤブキリ(成虫が見つかりました!!)
アカシジミやミズイロオナガシジミといった森林性シジミチョウ
やたらと目につくマイマイガの幼虫、草むらにはトノサマバッタの幼虫
足元を徘徊するイワワキオサムシ等、昆虫相はもうすっかり初夏の顔ぶれになっていました。
トビモンオオエダシャクの幼虫が桜の枝に擬態している姿をみんなで探しました!
今年は 生きものの見つけ方=かくれんぼ をテーマにしています!
次回は7月6日(土曜日)10時から です。お昼をはさんで午後まで。
お問い合わせは、根来山げんきの森倶楽部に!
ではこの昆虫は? だれの子どもでしょうか?
岩出図書館近くの草はらにいました。
撮影 2019年5月5日
こんどは背中に筋が2本 キリギリスの幼虫!?

記事掲載から約2ヶ月たち、そのころ見かけた幼虫は、そろそろ成虫になる時期です。
我が家の庭では、6月に入ってから ギー ギー と力強い鳴き声が聞かれるようになりました。 キリギリスかな!?
キリギリス類の姿や鳴き声にこれからも注目しましょう♪